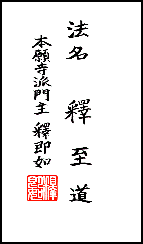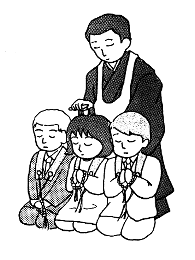
1.「法名」は生前にいただくものです。 浄土真宗門徒として、心から阿弥陀さまを敬い、そのみ教えに生きることを表明する儀式を「帰敬式(ききょうしき)」と言いますが、 この帰敬式に際して、ご門主さまより「おかみそり」を受け、いただくのが「法名(ほうみょう)」です。「法名」は、仏さまのみ教えに生きることを決意した人に与えられるものであり、仏弟子であることをあらわす名前 〔ブディストネーム〕です。 浄土真宗の葬儀においては、おおかたの場合、「法名」が〔故人がそれをいただいておられなかった場合は、所属寺の住職がおつけして〕葬儀壇に飾られますので、法名=死者の名前と理解されがちですが、「法名」は、決して死者につけられる名前ではありません。私たちは、浄土真宗門徒としての自覚を深める意味でも、生前にできるだけ早い機会に「帰敬式」を受けたいものです。 |
|
2.「法名」の起源は、仏教の平等思想です。 お釈迦さま在世の頃は、出家剃髪して法衣を着すれば、みな等しく沙門釈子(この出家者は釈迦の子どもという意)と呼ばれていました。そして仏教が中国に伝えられてから、現在のような形式の「法名」が生まれました。中国では実名の他に字(あざな=生者)、諱(いみな=死者)を持つ習慣があり、それが仏教に影響を与えたものと思われます。 さらに中国では、最初、出家した者の多くは、師の姓をとって自己の姓としていましたが、東晋時代に、道安という僧は、仏弟子はお釈迦さまのお心を体して、皆平等に「釈」をもって姓とすべきであると唱えて、自ら釋道安と名のりました。現在、私たちの宗門〔浄土真宗〕で法名を「釋〇〇」としているのは、ここに由来します。〔右のカットは、帰敬式でいただく法名です。〕 |
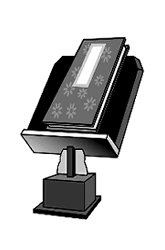
3.「法名」と「戒名」は違います。 仏事というものは、一見するとどの宗派も同じように見えますが、宗派によって形態が違い、意味合いも違っています。 浄土真宗では、戒名とは言いません。戒名は、厳格な規律(戒律)を守って仏道修行する自力聖道門(しょうどうもん)の人々につけられる名前であり、阿弥陀仏の本願力に信順して生きる私たちがいただく名前は「法名」です。従って、「法名」には修行の経歴を表す道号(いわゆる、四字や六字の戒名)や、修行の形態を表す位号(信士・居士・信女・大姉等)はありません。「法名」は「釋〇〇」というただそれだけです。字数が多いほど値打ちがある訳ではありません。 亡くなられた人の法名は、お位牌ではなく、右のような過去帳に記載します。 |