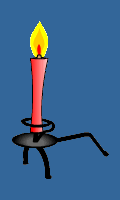平成20年年頭挨拶
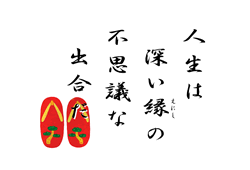
年の暮れに、その年を表す「一文字」が発表されます。それを清水寺の管長さんが揮毫する光景が、テレビでも放映されます。
昨年の言葉は、「偽」でした。この言葉を書きながら管長さんも、こんな世相に怒りを露わにしておられました。管長さんも、「赤福」を食べ、船場吉兆へ通っておられたのかも?
そう言う私も京都へ行く度に、帰りには「赤福」をおみやげにしていたので、今、残念でなりません。でも、美味しい、美味しいと言って食べて、何ともなかったので、「気の持ちよう」という感じがしない訳でもありません。けれども、知っていながら他人を欺く、その魂胆は、やはり許せません。
不特定多数を相手に、商売をしたり、イベントをするようになったのが、現代社会です。インターネットなどの通信もそうです。そこでは、人と人との直接的で、親密なつながりよりも、いかに多くの人を集めるかが問題であるので、「見せかけ」や「偽装」が横行するのは、ある意味、必然であったのかも知れません。
今年の正月の門前の掲示板には、「人生は 深い縁(えにし)の 不思議な出合いだ」という坂村真民さんの言葉を掲げました。
仏教では、過去の世からの深い因縁によって、人間界に生まれたのであると言われます。〔「それ人間界の生を受くることは、まことに五戒をたもてる功力(くりき)によりてなり。これおほきにまれなることぞかし。」(『御文章』2帖7『浄土真宗聖典註釈版』P1118)〕
その生れがたい人間界での出合いもまた、不思議な縁であります。「袖振り合うも他生の縁」ということわざがありますが、その出合いの不思議を不思議と感じるところに、人生の喜びはあるのではないでしょうか?
法律の規制や、マスコミの突き上げで、「見せかけ」や「偽装」が無くなるものではありません。そのような外部の圧力によるのではなく、自らの内に「そうせざるを得ないセルフコントロールがはたらく」ことが健全な社会ではないでしょうか?
先ずは、人と人とが直接に出合う、ふれあうこと、相手の顔を見ることが大切ではないでしょうか?
お寺は、仏さまが居ますところ、また、仏の教えが生きるところ、そしてまた、仏の慈悲につつまれ、仏の智慧に照らされた人々が集うところです。そこには、「見せかけ」や「偽装」は要りません。「ありのまま」で迎えられるところです。
浄蓮寺開基400年はもう2年後、親鸞聖人750回大遠忌は3年後に迫っています。今年からもう、その法要期間中であるとの位置づけで、種々の法要記念イベントを開催します。どうぞ、老若男女、多くの方々のご参集をお待ちしています。